聖書と典礼
『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)
 きょうの福音箇所をさらに深めるために
きょうの福音箇所をさらに深めるために
和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第23主日
 このページを印刷する
このページを印刷する
| 2025年9月7日 年間第23主日 C年 (緑) |
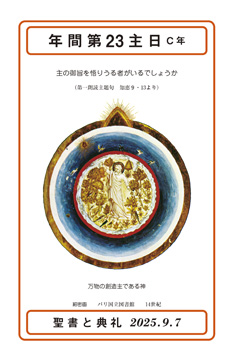 主の御旨を悟りうる者がいるでしょうか (第一朗読主題句 知恵9・13より) 主の御旨を悟りうる者がいるでしょうか (第一朗読主題句 知恵9・13より)万物の創造主である神 細密画 パリ国立図書館 14世紀 きょうの表紙絵は、第一朗読箇所の知恵の書9章13-18節の冒頭「神の計画を知りうる者がいるでしょうか。主の御旨を悟りうる者がいるでしょうか」(13節)にちなみ、創造主としての神を描く細密画が掲げられている。朗読箇所の中で、直接創造のことは触れられていないが、17節の「天の高みから聖なる霊を遣わされなかったなら、だれが御旨を知ることができたしょうか」や、また答唱詩編の第一連(詩編90・3+5ab「あなたは人に、『もとにもどれ』と仰せになり、人はちりにもどされる。あなたがいのちを絶たれると、人は眠りにおちいる」(典礼訳)など、神の計画の最初の発現である、天地創造、とくに人間の創造の出来事(創世記2・7参照)が思い出される。 この絵は、神を老人の姿で描き、地上のさまざまな動植物に囲まれている光景になっている。そしてこの球体の周りに海とも空ともいえる青の濃淡の中に、白い鳥が舞っている様子が描かれる。その中でも放射する光が描かれている部分がある。これは神の働きを特に示す星や天界の象徴なのであろう。 いずれにしても、我々は、自分たちの生存の基盤・当然の環境である時の巡り、昼夜の交替、天体の動きなどすべてが、神からのものであるという原点に立ち戻ることが「神の計画」「主の御旨」を尋ねるよう求められている。「あなたの望まれる道」(知恵9・18)はどこにあるのか?……と。 この箇所が第一朗読に選ばれているのは、きょうの福音朗読箇所ルカ14章25-33節に対するヒントとなるからである。きょうの福音朗読箇所にもイエスの語る直接的なメッセージがたくさん。「自分の十字架を背負ってついて来る者でなければ、だれであれ、わたしの弟子ではありえない」(ルカ14・27)ということばから、“自分の十字架を背負ってからわたしについて来なさい”という呼びかけが聞こえるだろう「十字架」という語には、当然に、イエス自らが受け入れて担うことになる苦難の全体が予示されている。同時に、「十字架」には、たとえそれを各自が一人で担わなければならないものであるにしても、それはイエスがともに担ってくれるものなのだ、というメッセージも含まれている。 この呼びかけは、今我々にも迫られる「神の計画」「主の御旨」への問いかけであろう。それは、神自身が「知恵」を、そして「聖なる霊」を我々に与えてくれなくては知ることも悟ることもできない。逆を考えると、神が「知恵」や「聖なる霊」を我々に与えてくれているから人は必ずや悟ることができる、ということの確約でもある。 福音の中のイエスのことばは、さらに十字架を背負って彼に従う道の厳しさを示している。一方で、「父、母、妻、子供、兄弟、姉妹」といった家族よりも、自分の命よりも、何よりもイエスに従うことを優先させるように(ルカ14・26参照)との呼びかけ、そして「自分の持ち物を一切捨てないならば、あなたがたのだれ一人としてわたしの弟子ではありえない」(ルカ14・33)という呼びかけにまで極まる。この厳しい求めは、後の時代に、信仰者が迫害を受けて、家族からも離され、すべての物を奪われ、自由さえも奪われたとき、力強い保護と導きの力となっていったに違いない。さらに、修道者たちが、財産を捨て、家族とも離れ、あえて神とキリストのために孤独を選び、祈りと礼拝に専念する生涯を選ぶときの、最大の指針、招き、導きになっていったに違いない。我々にとっても、キリストに徹底して従うべくキリストが求める愛の掟に従って、人との家族的な交わりを大切にし、財産を善用していく生き方へと招かれていくことになる。そのとき、人間関係・家族関係・財産などに振り回されたり、とらわれたりするのではなく、あくまで主体的に振舞うことができるようになる。 このようなあたりに触れるのが、福音朗読箇所の中間にある譬(たと)え、すなわち、塔を建てようとする者(ルカ14・28-30参照)、敵の軍勢をより少ない兵を迎え撃とうとする者(14・31-32参照)の話なのではないだろうか。そこで求められるのは繰り返される「まず腰を据えて」(14・28、31)という語句に暗示される、じっくりと神の計画を尋ねつつ考え、行動する生き方なのであろう。 第1朗読の祈りは、そのような「腰を据えて」考える人の態度を、神からの「聖なる霊」(知恵9・17)、「知恵」(同18節)にゆだねる姿勢として表現されているように思われる。第二朗読のフィレモンへの手紙(9b-10、12-17)も当時の社会状況の中で逃亡奴隷となったオネシモのことについてさまざまな側面を考慮しながら元の主人フィレモンに配慮を求める慎重な態度が浮かび上がる。パウロなりに「腰を据えて」究極的には神の望まれる方向を探ろうとする姿勢である。目指されていくのは身分関係を超えた「愛する兄弟」(同16節)の関係であり、「仲間」(同17節)としての関係である。 十字架のイメージが強烈な、きょうの福音であるが、そのメッセージは、我々の社会の中での生き方、共同体形成といった信仰実践のテーマに息吹を注いでいくようである。創造主である神の姿を仰ぎながら、自分たちの周囲や社会にもまなざしを向けていくよう呼びかけられている。 |
和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第23主日